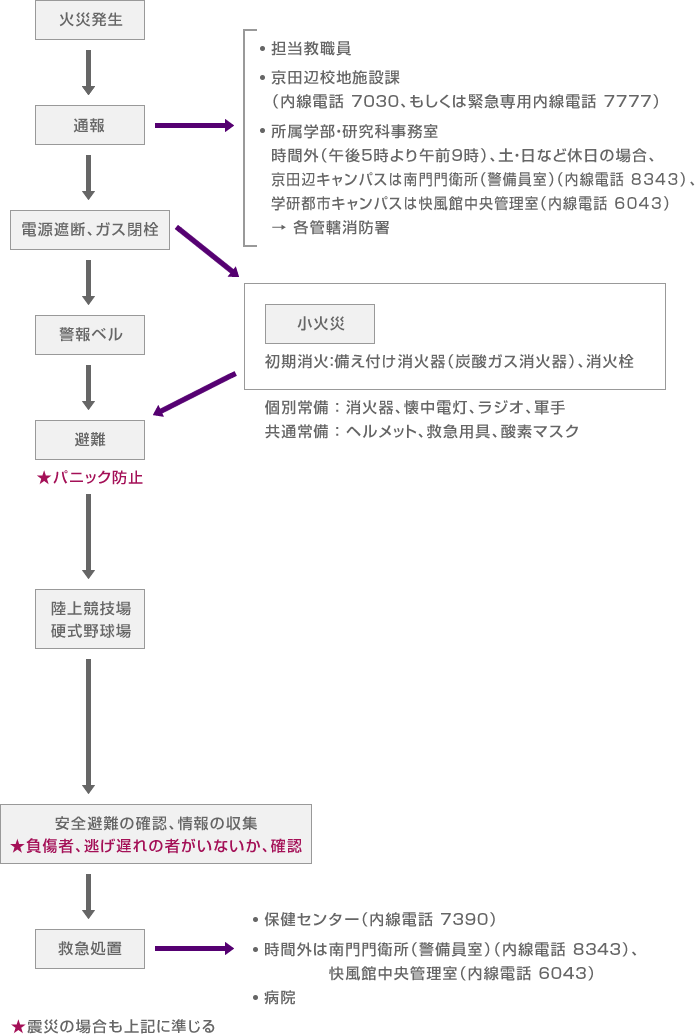実験環境における防災安全
大学の実験環境において、教育・研究を円滑かつ効果的に行う上で、多種多様の機器・薬品類の使用は不可避であります。また、これら機器・薬品類の危険性を熟知し、しかも適切な管理下で使用しなければなりません。加えて、火災、地震、その他予期せぬ突発事故の発生を想定し、緊急時の対策を講じておく必要もあります。以下、緊急時の基本的な行動指針をまとめております。
緊急時の基本的な行動指針
火災発生時
通報
担当教職員、研究室責任者へ(部署ごとに、連絡先、電話などを決め周知しておく)
(1)午前9時~午後5時
京田辺校地施設課へ(内線電話 7030、もしくは緊急専用内線電話 7777)
所属学部・研究科事務室へ
(2)午後5時~午前9時、土・日、祝日、創立記念日、キリスト降誕日、夏冬期休暇中の一定期間
<京田辺キャンパス>
| 南門門衛所(警備員室)へ (内線電話 8343) |
→ | 南門門衛所より消防署へ連絡 (火災報知器→南門門衛所へ) |
|
<学研都市キャンパス>
| 快風館中央管理室 (内線電話 6043) |
→ | 快風館中央管理室より消防署へ連絡 | |
初期消火
(1)電源遮断
各実験室分電盤内の主開閉器を開く、ガス元栓を閉じる
(2)備え付け消火器を用いる(置き場所の明示)
| 炭酸ガス消火器 | 有機溶剤の引火や電気による火災の初期に有効で、消火後の被害も少ない |
|---|---|
| 粉末消火器 | 小火災から大火災に用いる |
| 泡消火器 | 火災が広がった時に用いる |
研究・実験室では、炭酸ガス消火器が取り扱いやすく有効である
(3)消火栓を用いる
(4)火災発見時および消火不能の場合、火災報知器の発信機押しボタンを押す(火災断定となる)。
避難経路
状況によって手に負えないと判断された場合、速やかに屋外へ退去する。避難経路(予め確認しておく)および館内放送等の指示による。逃げ遅れた者がいないか確認する。また避難時には、エレベータを使用しないこと。
| 報辰館(HS) | 避難階段(各階東,西側) |
|---|---|
| 有徳館西館(YE) | 避難階段(各階東,西側,中央) |
| 有徳館東館(YM) | 避難階段(各階東,西側) |
| 至心館(SC) | 避難階段(各階東,西側,中央) |
| 香知館(KC) | 避難階段(各階中央) 避難はしご(2,3階西側) |
| 光喜館(KK) | 避難階段(各階東,西側) |
| 恵喜館(KE) | 避難階段(各階東,西側) 救助袋(3,4階教員研究室前廊下南側) |
| 創考館(SO) | 避難階段(各階東,西側) |
| 夢告館(MK) | 避難階段(各階東,西側) 固定式緩降機(3,4階廊下東側) |
| 医心館(IN)南棟 | 避難階段(各階東,西側) |
| 医心館(IN)北棟 | 避難階段(各階中央南,西側) 救助袋(4階東側及び3,5階東側共同実験室内) |
| 訪知館(HC) | 避難階段(各階東,北側) 救助袋(3階南西側ベランダ,4階大学院共同研究室内) |
| 磐上館(BJ) | 避難階段(各階東,北側,中央) 避難袋(3階BJ335多目的実習室前廊下東側) |
| 香柏館(KHH)高層棟 | 避難階段(各階西側,中央) |
| 香柏館(KHL)低層棟 | 避難階段(各階中央) |
※防災シャッターは自動的に閉鎖する
震災発生時
| 出火防止 | 火気使用設備・器具の使用停止および確認 |
|---|---|
| 火災発生時 | 火災発生時の対処法に準じる |
| パニック防止 | 館内放送、携帯用拡声器を活用し冷静に対処する |
| 避難誘導 | 学内運動場など広域避難所へ誘導する(エレベーターは使用しない) 避難時は落下物や火災などに注意し、頭や足などの防護に努める |
| 情報収集 | 被害状況および負傷者の把握に努める 防災関係機関からの情報収集 |
ケガ・救急
通報
担当教職員、研究室責任者へ
救急処置
保健センター(内線電話 7390)へ連絡
夜間または時間外の場合、京田辺キャンパスでは「南門門衛所(警備員室)(内線電話 8343)」、学研都市キャンパスでは「快風館中央管理室(内線電話 6043)」に電話し、必要な場合は救急車を要請する
ケガ、病状を伝え、医師、看護師の指示に従う
| 裂傷、切傷 | 止血 |
|---|---|
| 火傷 | 冷水で冷やす(30分) |
| 薬品中毒 | 吐かせる、換気 |
AED
京田辺キャンパス23ヶ所、学研都市キャンパス1ヶ所、多々羅キャンパス2ヶ所( AED設置場所[PDF 419KB]を参照すること)に設置されている
保健センター
9:00~17:00(土曜は12:00まで)(内線電話 7390)
京田辺キャンパス近くの救急病院
| 田辺中央病院 | 電話 0774-63-1111 近鉄・新田辺駅より北西へ3分 |
|---|---|
| 京都きづ川病院 | 電話 0774-54-1111 京田辺キャンパスより北東へ車で25分、近鉄・大久保駅よりバス5分 |
| 宇治徳洲会病院 | 電話 0774-20-1111 近鉄・小倉駅より北東へ車で6分、徒歩20分、京田辺キャンパスより車で約30分 |